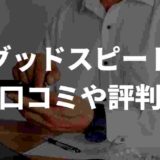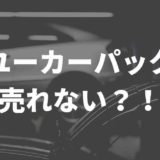このサイトは当社の取材調査を元に記事を作成しております。サイトには一部プロモーションが含まれている場合がございます。
ガソリン価格いつ下がる?今後どうなる?ガソリン価格の決まり方や価格の推移などから徹底予想

2021年から高騰しているガソリン価格は、ドライバーにとって頭の痛い問題です。政府による補助金が投入されていながら170円/L前後で推移しているので、実質的には200円/Lを超えています。
そんなガソリン価格について、価格がどのように決まりどのような要因で高くなっているのかと、価格の推移と世界情勢を考えながら、今後のガソリン価格を予想していきます。
車を売りたい!
そんな人にはカーセンサーおすすめです。

https://kaitori.carsensor.net/
\愛車を提示最高額※で売却しよう!/
目次
ガソリン価格の中身はどうなっているのか

皆さんがご存じのとおり、ガソリンは原油から精製される石油製品の一種で、日本国内ではオクタン価の違いからハイオクガソリンとレギュラーガソリンの2種類が流通しています。
いずれもリッター当たりの価格表示となっていて、最近の価格高騰からその中身についても知られるようになってきました。
まずはガソリン価格の内訳や最終的な販売価格がどのように決まっているのか、詳しくチェックしていきます!
ガソリン価格の決まり方
上がった!下がった!と一喜一憂しているガソリン価格ですが、普段ガソリンスタンドで給油するときの価格には、非常に多くのコストがかかっています。
ガソリンは元が原油で、日本はそのほとんどを輸入に頼っているため、原油の購入代金や産油国から日本へ運ぶための輸送費や事故などに備える保険料が必要です。また原油の決済はドル建てで行うので為替の影響も受けます。2022年に進んだ円安が原油購入コストに悪影響を与えたのは理解できるでしょう。ここまでが日本に原油が入ってくるまでのコストです。
原油のままでは使うことができないので、製油所で精製されガソリンにするコストと、ハイオクにはオクタン価を高める添加剤や、燃焼した添加剤の燃えカスを洗い流す洗浄剤を点火するコストもかかっています。これがレギュラーガソリンと約10円の価格差が生まれる要因です。
精製されたガソリンは、ガソリンを販売する小売事業者へ配送されますが、とうぜんここでも輸送費がかかり、ここまでの一連の事業を行っている石油元売り各社の人件費や利益が上乗せされます。さらに小売事業者へ卸す価格には、すでに一般的にガソリン税といわれる「揮発油税及び地方揮発油税」が課税されています。
こうして決められた石油元売りからの卸価格に、1リッターあたり平均8円~15円といわれているガソリンスタンドの利益がプラスされたのが販売価格になっています。
高止まりする原油価格

ガソリン価格が変動する理由のほとんどは、原油価格と輸送費、そして為替の影響によるものです。その中でもニュースでも頻繁に取り上げられるとおり、原油価格が高止まりしていることがガソリン高に直結しています。
ニューヨーク・マーカンタイル取引所のWTI先物取引価格を見るのが、原油相場を知る基本となり、2020年10月以降の推移から上昇ぶりが分かると思います。価格は1バレル(約159L)当たりのドル価格です。
| 2020年10月 | 39.53$ | 2021年6月 | 71.38$ | 2022年2月 | 91.74$ |
| 2020年11月 | 41.10$ | 2021年7月 | 72.46$ | 2022年3月 | 108.49$ |
| 2020年12月 | 47.05$ | 2021年8月 | 67.73$ | 2022年4月 | 101.78$ |
| 2021年1月 | 52.10$ | 2021年9月 | 71.56$ | 2022年5月 | 109.60$ |
| 2021年2月 | 59.06$ | 2021年10月 | 81.32$ | 2022年6月 | 114.59$ |
| 2021年3月 | 62.35$ | 2021年11月 | 79.18$ | 2022年7月 | 99.85$ |
| 2021年4月 | 61.71$ | 2021年12月 | 71.53$ | 2022年8月 | 91.57$ |
| 2021年5月 | 65.18$ | 2022年1月 | 83.12$ | 2022年9月 | 83.87$ |
実はこのチャートの少し前になる2020年4月には、原油価格がマイナスになるという衝撃的なニュースがありました。それはコロナ過による原油需要の急減と、産油国の減産調整失敗が原因だったのですが、2020年12月から原油価格の上昇が顕著になっていくのは、世界がコロナ後に舵を切ったからです。
さらに注目なのは、2022年2月にロシアのよるウクライナ侵攻後の急騰で、原油供給量が需要に追い付いていない状況が続いています。
多くの割合を占めている税金

もう多くの方がガソリンに課税されている多額の税金批判をニュースなどで目にしているでしょう。現在のガソリンには、良いか悪いかは別にして以下の税金が課税されています。
- ガソリン税 ・・・ 先ほども説明したとおり正式には「揮発油税及び地方揮発油税」という名称です。ガソリン税は2階建てとなっていて、1階部分に当たる本則税率28.7円/Lと、2階部分にあたる暫定税率25.1円/Lの、合わせて53.8円/Lが課税されています。暫定といいながら恒久化していることが度々問題視されていて、ガソリン価格高騰時に暫定税率を停止する、いわゆる「トリガー条項」を政府が無視していることも批判の対象となっています。
- 石油石炭税 ・・・ エネルギーの安定供給対策などに充てられる財源で、ガソリンを含む石油製品や天然ガス、石炭などに課税されています。ガソリンには04円/Lが課税されています。
- 地球温暖化対策税 ・・・ 地球温暖化対策のためCO2削減を推進する目的で2012年10月1日から導入された目的税です。導入から段階的に引き上げられていて、現在は0.76円/L課税されています。
- 消費税 ・・・ 今は税率が10%にもなった「消費税及び地方消費税」ですが、これも度々非難されています。それというのも、ここまで紹介したガソリンに課されている各種税金に、さらに消費財が課税される「二重課税」が疑問視されているからです。これには諸説あるので深掘りしませんが、価格高騰がダイレクトに跳ね返る消費税の負担はかなり大きなものがあります。
レギュラーガソリンの価格が170円/Lだとしたら、ガソリン税53.8円と石油石炭税2.04円、地球温暖化対策税0.76円に加え、消費税が15円で合計71.6円の税金になるので、ガソリン価格の約42%が税金ということになります。
やはり負担感が大きいと言わざるを得ませんよね…
流通コストや販売者の利益と補助金
ガソリン価格の高騰は、皮肉なことにガソリンを配送するコストまで上昇させていて、それも価格高騰に結びついています。
ここで不思議に思うのは、2022年1月27日から始まった「ガソリン価格高騰を抑えるための石油元売り各社に投入する補助金」が、販売価格に反映されているかということです。
これについて、こんな補助金を止めたいと思っているはずの財務省が関東財務局管内で調査を行い、10月にその結果を発表しました。それによると「補助金分価格が抑制されている」と回答したガソリンスタンドは45.2%に留まり、「抑制されていなし」23.2%、「わからない」31.6%となっています。
つまり12月まで3兆円もの補助金を投入して、そのうちかなりの金額がガソリン価格抑制ではなく、石油元売り各社あるいはガソリンスタンドの利益になっている可能性が高いのです。
原油価格が高騰している原因と今後の見通し

家計や物流コストにダメージを与えているガソリン価格の高騰は、原油価格の高騰と連動しています。つまり原油価格が高騰している原因を知り、それが今後改善していくのか考えることで、ガソリン価格がどうなっていくのか推し量ることができるのです。
ここからは日本が輸入に頼っている原油価格が高騰している原因と、それらの今後の見通しについて考えてみます。
コロナショックと産油国の減産
先ほども触れましたが、コロナショックによる世界的な原油需要の激減は、産油国に多くのダメージを与えました。原油価格が下がると産油国は価格維持のため協調して減産へ移行するのですが、欧米諸国がコロナ後へ舵を切ると景気拡大への期待から原油需要が急激に高まり、それに産油国の生産が追い付かない事態となったのです。
この状況に対し中東を中心とした産油国は、原油増産に慎重な姿勢をとっています。それは政権が変わるたびにエネルギー政策がブレるアメリカや、急激な断炭素化を推し進めてきたEU諸国への不信感が根底にあるうえ、後述する理由で簡単に増産ができなくなっています。
産油国が増産に前向きになっても、少なくとも5年程度は実現できないのでは…
環境問題を優先したバイデン大統領
よく知られているとおり、アメリカの前大統領のトランプ氏は、地球温暖化はウソだと言い切り「反脱炭素派」でした。シェール革命といわれた石油増産を推し進め、原油価格の低下に一役買っていたわけですが、バイデン氏が大統領になるとアメリカのエネルギー政策は一変します。
バイデン大統領は、気候変動対策の国際的枠組み「パリ協定」へ復帰し、EUの主導する脱炭素路線へ歩調を合わせました。実は原油価格の上昇は、バイデン大統領の取り組みと完全に連動しており、原油価格が高止まりを見せている大きな原因だと思われます。
今後の見通しについては、バイデン大統領が現職のうちは変わらないと考えられるので、少なくとも2024年まではマイナス要素といえるでしょう。
砂上の楼閣だった脱炭素という幻想

車好きの方多くは、数年前からEUが強烈といえるほど推進してきた「脱炭素」に懐疑的な目を向けていたのではないでしょうか。
EUが目指す脱炭素は、すなわちエネルギー源として原油を除外する政策そのもので、イデオロギーともいえる極端さは、原油生産への投資を押し下げる結果となりました。
油田の開発維持には膨大な投資が必要なのですが、それがここ数年滞ったため、急な原油需要増大に産油国が対応できないことになったのです。
エネルギー政策の失敗のツケは、脱炭素の先頭を走っていたドイツ自身が石炭など買い漁っているせいで、発展途上国にまで及んでいます。
極端な極右政党の台頭などない限り、イデオロギー政策と化した脱炭素の旗を降ろす気配はないようで、これもガソリン高にとってはマイナス要素といえるでしょう。
ロシアのウクライナ侵攻
EUの脱炭素と話が繋がりますが、ロシアによる不法なウクライナ侵攻も原油価格の暴騰に大きな影響を与えました。
それはロシアが大きな産油国だったことと、戦争に反対する欧米諸国がロシア産原油の輸入を禁止たことに起因しています。とくにドイツが極端なエネルギー政策へ舵を切っていたことから、ロシアへのエネルギー依存度が高く、混乱に拍車をかけています。
戦争の帰趨は分かりませんが、少なくともロシアが現政権のままでいるかぎり、原油相場にとっては良いことはありません。
大きく値を下げてしまった日本円

2022年に入ってから極端に進んだ円安は、一つには日本をのぞく先進国がアフターコロナへ舵を切ったことで、日本をのぞく先進国の景気が急回復したことにより始まりました。
景気拡大に追いつかないサプライチェーンの混乱や、急な人手不足は各国でインフレを引き起こし、各国中央銀行は利上げを進めたため日本との金利差が円安を招いたといわれています。
円安は、原油の調達を輸入に頼る日本にとってコストアップにしかならず、ガソリン価格高騰の大きな要因
不確定要素は多いものの、アメリカの中央銀行が利上げのスピードを落とすという観測が出始め、円安のピークは脱しつつある可能性は高いでしょう。そうなれば原油輸入価格は低下し、結果としてガソリン価格が落ち着くことになります。
今後考えられるガソリン価格のシナリオ
確定的なことは言えませんが少なくともガソリン価格は、「下がる」「上がる」「変わらない」の3パターンの組み合わせしかありません。
最後に今後考えられるそれぞれのシナリオについて考えてみましょう。
ガソリン価格が下がるシナリオ

ガソリン価格が下がるのは、原油価格の低下か極端な円高、もしくはガソリンに課されている税金の廃止くらいしか考えられません。
では原油価格が下がるのはどのような場合なのでしょうか。原油もモノなので需要と供給のバランスで価格が決まります。供給が増えるための条件は設備投資の継続的増加しかないのですが、欧米諸国が脱炭素教を唱え続けるかぎり望み薄といえます。
逆に需要が減るケースですが、それはコロナ過のような極端かつ世界的な不況が起こることと同義です。しかし今のインフレに対する各国の対症療法を見ていると、景気後退の可能性は大いにあり得ます。
しかしその場合は、日本も不景気に見舞われる可能性が高いので、ガソリン価格は下がっても買うための収入が落ちていることになっているでしょう。
そう考えていくと円高によるガソリン価格低下が、一番可能性が高いのかもしれません。
高値のまま推移してしまうシナリオ

残念ながら可能性が一番高いシナリオは、ガソリン価格が高騰したまましばらく続くというものです。
現在1リッターあたり35円を上限としたガソリン補助金が続いていますが、12月末までの期限を来春まで延長する方向で検討されているようです。もしこれがなくなれば、悪夢の1リッター200円超えの可能性もあるので、心配の種といえます。
地政学的リスクも考慮する必要あり
ロシアによるウクライナ侵攻は、日本から遠く離れた場所で行われていることですが、多くの方は中国と台湾のことを想像したのではないでしょうか。
もし中国が台湾を併合するための行動に移ったとき、それは日本が参戦するしないにかかわらず、シーレーンを塞がれることを意味します。つまり原油の輸入がストップしてしまうことになるでしょう。
そんなことになれば、1リッター200円どころか300円や500円もない話じゃありません。このような地政学的リスクも考えなくてはいけない世界になっているのです。
自動車関連税制の見直しは不可欠か

よく言われることですが、日本は世界的に見ても車の維持費が高い国です。ガソリンに課されている税金は先ほど説明したとおりで、これらも見直しの議論が必要になっていくのだと思います。
また自動車税や自動車重量税も、古い車には重い税金を課すなど、かつて日本の美徳だった「古いものを長く大事に使う」ということに反していないのでしょうか。
他人事だとは思わず、ドライバーひとり一人が考えるべき時なのかもしれません。
まとめ

2021年から急激に上昇してドライバーの家計の負担になっているガソリン価格ですが、詳細を分析してみると短期的には明るい未来は見えないようです。この機会に、燃費のいい車に乗り換えてみては?
車を1円でも高く売りたい!そんな人にはカーセンサーおすすめです。

https://kaitori.carsensor.net/
\愛車を提示最高額※で売却しよう!/